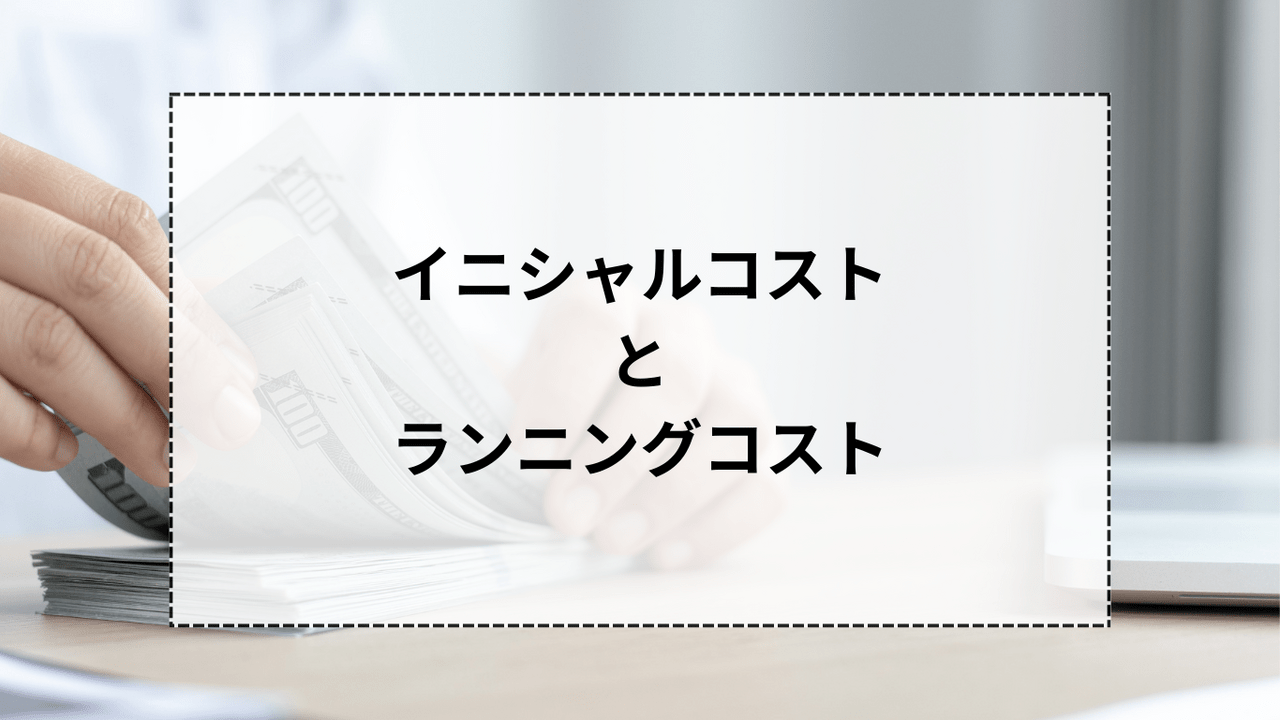
新しいサービスやツール、設備を導入する際、多くの人がまず注目するのが「初期費用」(=イニシャルコスト)です。
「イニシャルコストが高いから、やめておこう」
「初期0円のサブスクのほうが手軽で良さそう」
こうした判断は決して間違いではありませんが、初期費用(イニシャルコスト)だけで比較するのは危険です。むしろ、本質的に見なければならないのは、長期的に発生する“ランニングコスト(維持費・運用費)”を含めた“総コスト”の設計です。
このコラムでは、イニシャルコストとランニングコストの違いを整理したうえで、実際の企業事例も交えながら、賢い意思決定のヒントをお届けします。
そもそもランニングコストとイニシャルコストの意味は?何が違うの?
用語の基本:イニシャルコストとランニングコスト
| 用語 | 意味 | 代表例 |
| イニシャルコスト(Initial Cost) | 導入・購入など、初期段階にかかる費用 | 設備投資、初期開発費、導入コンサル費用など |
| ランニングコスト(Running Cost) | 継続的な運用・維持にかかる費用 | 月額料金、保守費、人件費、更新費など |
例えるなら、家を買う時の「頭金」と「ローン返済・管理費」の関係に近いものです。
よくある「安さの落とし穴」
近年は、SaaS型ツールや月額制のクラウドサービスの普及により、「初期費用ゼロ」で導入可能なプロダクトが急増しています。一見すると合理的で、試しやすく、経費処理もしやすい。しかし、ここにこそ大きな罠が潜んでいます。
たとえば、以下のようなケース
・月額課金型のツールを複数導入 → 毎月数万円の固定費に
・安価なレンタルサーバーを使い続けた結果、スピードやセキュリティに課題発生
・外注開発で安く作ったシステム → 保守性が低く、改善ごとに追加コスト
つまり、導入時だけでなく「使い続ける前提」で考える視点が重要なのです。
実際の企業例_意思決定を左右したコスト構造_
事例1:free VS 弥生会計_見かけの価格 vs 累計コスト_
ある中堅企業では、会計ソフトを選定する際、「freee(クラウド型)」と「弥生会計(インストール型)」で比較検討を実施。
最初はfreeeの手軽さに惹かれたが、試算してみると、3年後には弥生の方が安いという結果に。さらに、操作性・サポート体制・セキュリティを評価し、弥生を選択。
→ 初期の「導入しやすさ」よりも、3〜5年スパンでの累積コスト(TCO)を重視すべきであるということがわかりました。
事例2:Airtable_“拡張性の代償”に気づけなかったノーコード導入_
プロジェクト管理とデータベースを一体化した柔軟なノーコードツールとして人気のAirtable。E社では、Excelベースの情報管理から脱却するため、無料プランでの導入を開始。操作性が高く、UIも優れており、チームの満足度も高かったようです。しかし、業務全体がAirtableに依存するにつれ、以下のような課題が顕在化しました。
- ビューの数・自動化・API接続など、業務活用には有料プランが必須
- ユーザー数が拡大するにつれ、月額10万円以上の支払いにスライド
- データベースが複雑化した結果、エンジニアでないと管理困難に
また、機能が豊富な分、他部門への横展開にはマニュアル整備や教育の負荷もかかった。
→スモールスタートできるツールほど、「スケール時のランニングコスト」が上がる可能性を見積もるべき。
事例3:Chatwork──“無料導入定着”のはずが…
使いこないことから、サンクコスト化国産のビジネスチャットツールとして広く導入されているChatwork。
- 社内にすでに「LINE WORKS」やメール文化が浸透しており、Chatworkの利用率が伸びなかった
- 結果的に、有料プランへ移行したものの、アクティブユーザーは3割以下
- 「せっかく導入したから」と続けているが、**実質的には“使われていない有料ツール”**に
→ランニングコストは“利用実態に対する費用対効果”で評価すべき。「安いから」「無駄じゃないはずだ」と思い込んで継続すると、組織のサンクコスト化につながる可能性がある。
このように、無料/低価格で導入できるツールであっても、拡張性・定着性・組織との相性を見誤ると、かえって高コストな選択になることがあります。。
イニシャルコストが高いことは悪なのか?
必ずしもそうではありません。むしろ、「初期投資は高いが、その後の維持費が安い」「自社でコントロールできる構造」など、長期的な視点で優位性があるケースも多くあります。
例:買い切り型 vs サブスク型
| プラン | 初期コスト | 維持コスト | 3年後の累計 |
| サブスク型 | 0円 | 月額2万円 | 72万円 |
| 買い切り型 | 50万円 | 年間保守5万円 | 65万円 |
→3年後に逆転。使用期間が長い程、買い切り型の方がコスト効率が良くなることも。
見るべき4つの視点
・累積コストで比較する(TCO思考)
→ 初期費用+ランニングコストを3〜5年スパンで算出
・拡張性(スケーラビリティ)を加味する
→ 人数やデータ量が増えた時にどうなるか?
・業務への影響=“人的ランニングコスト”も想定する
→ ツールが業務にどう影響するか、習熟にどれだけ時間がかかるか
・最悪パターン時の「固定費の重さ」を想像する
→ 利用頻度が下がったとき、コストが身軽に調整できるか
最後に_”安さ”より”持続可能性”を_
イニシャルコストが安いという理由だけで選ぶと、後から「使い続けられない」ことになりかねません。逆に、高い初期投資があっても、その後の運用が安定し、組織にとって持続的に機能する選択であれば、それは「正しい“経済的選択”」です。
「今いくらかかるか」ではなく、
「3年後、自分たちの負担はどう変わっているか?」
要するに、「長い目で見た時のコストパフォーマンス」に留意していく必要があるでしょう。
それを想像できる企業ならば、コストをコントロールした戦略的な成長を実現できるのです。
参考資料:
・https://www.meti.go.jp/press/2022/04/20220411001/20220411001.html
・https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2023/honbun/index.html
・https://forbesjapan.com/articles/detail/39675
・https://newspicks.com/news/6365451/
・https://bizhint.jp/report/561206
最後までご覧いただき、ありがとうございました。今回の記事では、基本的なEXIT戦略の知識や流れなどをご紹介いたしました。
EXPACTでは、特にスタートアップ企業への補助金活用や資金調達を強みとしており、実績・経験も多数ございます。資金調達成功に向けて、パートナーを探している、また詳しく話を聞いてみたいという方はこちらからお問い合わせください。

