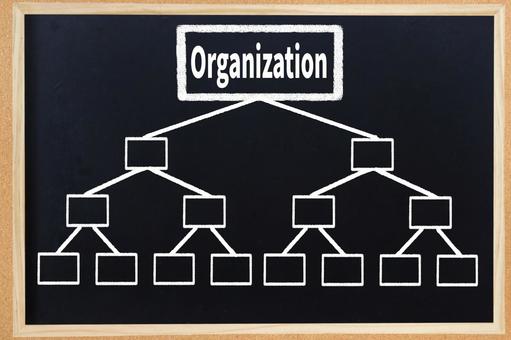
組織づくりやリーダーシップ論において、「全ての状況において絶対に正しい」という万能な組織の理論はあるのでしょうか?
おそらく、多くの人が「状況による」と答えるでしょう。実はまさにその発想を土台とした理論が「コンティンジェンシー理論(Contingency Theory)」です。
本記事では、その概要から理論モデル、具体的な事例、実践方法までをわかりやすく解説します。
コンティンジェンシー理論とは?
コンティンジェンシー理論は、「組織やリーダーシップの最適な形は、状況や環境によって異なる」とする考え方です。
つまり、あらゆる状況に通用する“絶対的な組織構造やリーダー像”は存在せず、環境に応じて柔軟に対応することこそが組織の成功要因である、という前提に立っています。
誕生の背景:リーダーは環境に適応すべき存在へ
1940年代までは、「リーダーは生まれつきの資質によって決まる」という考えが主流でした。しかし1960年代以降、社会・経済環境の急激な変化に伴い、組織やリーダーは“偶発的(contingent)な要素”に適応すべきだという視点が広がっていきます。
これが、現代の柔軟な経営・組織設計の基礎となったのです。
主なコンティンジェンシー理論モデル
コンティンジェンシー理論とは言っても、そのモデルは学者によって異なります。ここでは以下の主要な4つのモデルをご紹介します。
フィードラーのコンティンジェンシー・モデル
リーダーのスタイル(職務志向型/人間関係志向型)と、
・リーダーと部下の関係性
・タスクの明確さ
・リーダーの権限
という3要素を組み合わせて、最適なリーダーを導き出すモデル。
バーンズ&ストーカーの組織構造論
「機械的組織(ルールや階層が明確)」と「有機的組織(柔軟で分権的)」のどちらを採るかは、業界の安定性・変動性に依存するという視点。
ローレンス&ローシュの条件適応理論
分化(専門性)と統合(協働性)のバランスを環境に応じて調整できる企業は、パフォーマンスが高いとする理論。
ハーシー&ブランチャードのSL理論(Situational Leadership)
部下の成熟度に応じて、指示型・支援型などリーダーシップを柔軟に変えるというアプローチ。
現場での活用事例
ではこの理論に基づいて、実際のビジネスの現場ではどのように組織を形作っているのでしょうか?以下では実例を部門ごとに有効な組織形態とそれを実践する企業に分けて記述しています。
▷ 部門ごとの具体例
- 運輸部門:安定性が重視されるため、ヒエラルキー型(機械的組織)が有効。
- 製造部門:大量生産では標準化・効率重視の機械的組織、複雑な製品を扱う場合は柔軟な有機的組織が向く。
▷ 実践企業の例
- アップル社:製品や市場に応じてチームや体制を変え、技術革新に対応。
- シンガポール政府:政策と組織構造を柔軟に見直し続け、効率性を維持。
▷ 日本企業の危機対応
- 日本取引所グループ:災害・システム障害に備えた複数の対応プランを用意。
- ANA:長時間の機内待機に備えた対応策を策定し、顧客満足と職員の混乱回避を両立。
メリットと注意点
このように実際にビジネスの現場でも活用されているコンティンジェンシー理論ですが、メリットはもちろんデメリットも存在します。
メリット
- 変化に強い柔軟な組織づくりが可能
- 多様な人材や価値観を活かせる
- 新規事業や組織改革の推進力になる
デメリット・注意点
- ノウハウの標準化が難しく属人化のリスク
- 状況判断を誤れば逆効果になることも
活用のためのポイント
- 組織環境の整備
柔軟な人材配置・研修制度を整える。 - 多様な人材の活用
状況ごとに適したリーダーを選べる文化づくり。 - 定期的なフィードバックと分析
組織体制や方針の継続的な見直し。 - リスク別対応マニュアルの整備(コンティンジェンシープラン)
非常時に備えてシミュレーションと改善を繰り返す。
まとめ:変化の時代にこそ求められる理論
コンティンジェンシー理論が教えてくれるのは、「正解は常に変わる」という前提に立ち続けることの重要性です。
安定と変化、一貫性と柔軟性、標準化と多様性。これらをどうバランスさせるかが、いま組織に求められる経営力なのです。
VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代において、変化に適応できる組織こそが、持続的な成長を実現できるのです。
リーダーシップと組織の在り方に関心がある方は以下もご覧ください。
